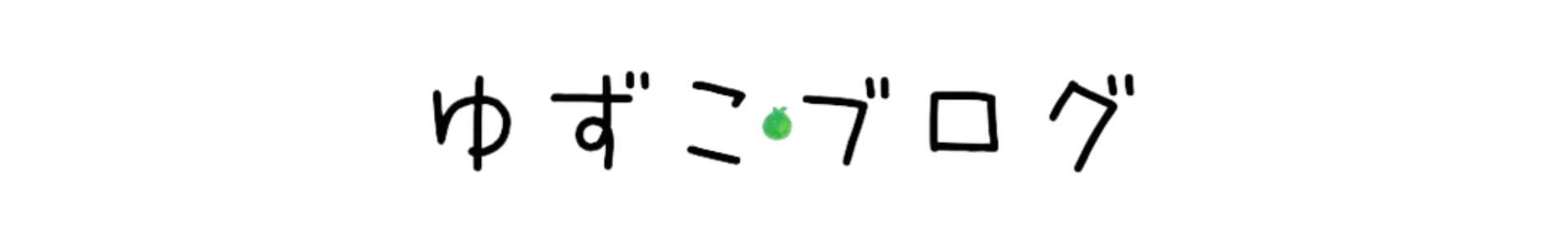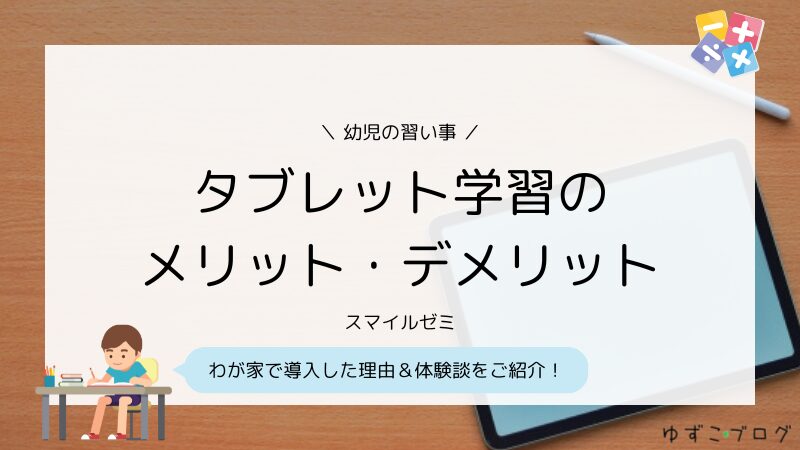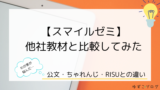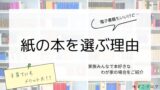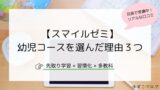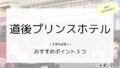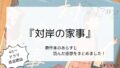「幼児期にタブレット学習ってどうなの?」
「スマイルゼミって実際どう?」
わが家では、長男4歳・次男3歳のタイミングで、スマイルゼミ【幼児コース】を導入しました。
親世代にはなかった「タブレット学習」。
正直なところ、始める前はかなり悩みました。
でも実際に使ってみて感じた、良かったこと・気をつけたいことがいろいろあります。
この記事では、タブレット学習を選んだ理由、メリット・デメリット、そしてスマイルゼミに決めた理由を、わが家の体験をもとにご紹介します。
- 幼児の習い事に何を選ぶか迷っている
- 幼児期から学習習慣を身につけさせたいと考えている方
- 教室への送り迎えが難しく、自宅で学習を完結させたい方
- タブレット学習のメリット・デメリットを知りたい方
▼スマイルゼミ他の記事をもっと読みたい方はコチラから▼
タブレット学習を幼児期に選んだ理由

小学校入学前に“学ぶ自信”をつけておきたかった
もともと、幼少期から学習系の習い事はさせたいと考えていました。
その理由は、小学校入学時に「勉強=楽しい」「自分はできるかも!」というポジティブなセルフイメージを持たせたかったからです。
学校で集団学習が始まると、「あ、これ知ってる!」と感じる子と、「みんなできてるのに、自分は分からない……」と感じる子がいます。
その最初の印象が、勉強への意欲や自信に大きな影響を与えると感じていました。

勉強の好き嫌いって、案外ここで
大きな分岐点がある気がしています。
大人になってもずっと、この“初期設定”のまま
自分を評価してしまうような……
大人になっても、何かしら勉強は続きます。
どうせ学ぶなら、苦手意識を持たずに楽しめた方が絶対におトク。
だからこそ、学びのハードルが低い幼児期から、学習習慣を身につけられたらいいな、と考えたのです。
赤ちゃん連れの送迎が難しく、自宅で完結したかった
長男の習い事を検討していたときの状況です。
- 長男4歳年少、年中から学習スタートしたい
- すでにスイミングは習っていた
- 次男1歳、赤ちゃん連れの送迎が大変
- 学習ドリルをやってみるも、うまくいかず
学習系の習い事を考え始めたころ、まず候補にあがったのが「KUMON(公文式教室)」でした。
親自身が子どものころに通っていて、馴染みがありましたし、ちょうどまわりの子も通い始めていた時期でした。
ところが、公文は週2回の教室通いが必要。
当時はすでにスイミングに週1回通っており、さらに下の子(次男)はまだ1歳。
赤ちゃん連れで長男の習い事に付き添うのは、思った以上にハードでした……。
ワンオペ育児だったこともあり、「これ以上習い事の送迎が増えるのは正直しんどい」と当時感じていました。
そのため、「自宅で完結する学習方法」に絞って検討することにしたのです。
市販のドリルは続かず、親子で疲弊……
自宅でできる方法として、まずは書店でドリルを購入し、家で取り組んでみることに。
ところが、長男まったく気乗りせず……

やる気のない子に、ドリルをさせようと必死な私。
親子ともにどんどん疲れていきました……
これでは本末転倒。
無理やり学ばせて勉強嫌いになったら、元も子もないと感じました。
そんなときに出会ったのが「タブレット学習」という選択肢。
「これからの時代を生きる息子たち、デジタル機器に親しんでおくのもまぁ悪くないか!」と前向きにとらえ、思いきって採用してみました。
幼児のタブレット学習で感じたメリット

子どもが楽しく学べる仕組みがある
タブレットでは、動画や音声を使ったコンテンツで学習できます。
視覚・聴覚に訴えるので、子どもが興味を持ちやすいのが特徴です。
英語のリスニングなども自然にできるのは、大きなメリットですよね。
学習後のミニゲームなど、ちょっとしたごほうび要素もあるので、楽しみながら自発的に取り組んでくれます。
学習ドリルでイヤイヤ勉強させられるよりは、よほど効果的だと感じます。

まずはタブレット学習を入り口に、
「勉強=楽しい」と感じてくれたら大成功!
学習習慣をつける“はじめの一歩”として活用しています。
「ごほうび要素がないと勉強しない!」となっては困りますが、そこは成長とともに調整していけばOKかなと。
学びへの第一歩として、タブレット学習は十分アリだと思います。
個別の理解度にあわせて学べる
タブレットは、子どもの学習データを記録・分析しながら、理解度に応じた問題を出してくれます。
苦手な部分を重点的に復習したり、得意な部分をさらに深められたり。
個別最適な学習ができるのは、とっても便利だと思います!
送迎不要で、毎日自宅で完結
先述したとおり、習い事の送迎は本当に大変。
子どもが複数人いたり、赤ちゃんだったり、イヤイヤ期の子だったりするとなおさらです。

予定通り動いてくれる日なんて、
ほとんどありません!
習い事に間に合うか、毎回ヒヤヒヤしています……
しかしタブレット学習なら、そのストレスもありません。
わが家では毎朝、登園・登校前の15〜20分を「スマイルゼミの時間」にしています。
自宅で完結してくれるのって、想像以上にありがたいです。
無理なく続けられるうえに、教室への移動時間も不要なので、生活リズムにも心にもゆとりが生まれました。
月額料金が比較的リーズナブル
教室型の学習と比べると、タブレット学習は月額料金が手ごろなのも魅力。
ざっくりですが、年中児を想定して比較してみました。
| 学習教室 | 月額の目安 |
|---|---|
| 公文(1科目) | 7,150円~ |
| 学研教室 | 6,930円~ |
| 七田式教室 | 15,400円~ |
| ドラキッズ | 11,000円~ |
| タブレット学習 | 月額の目安 |
|---|---|
| スマイルゼミ | 3,630円~ |
| こどもちゃれんじ | 1,980円~ |
| RISUきっず | 2,948円~ |
※いずれも最安プラン・教材費別・コースによって料金は異なります。
教室型とタブレット型では、明らかに価格帯が違いますよね。
タブレット学習はコスト面でも続けやすく、浮いた分を他の習い事や体験にまわせるのも嬉しいポイントです。
幼児のタブレット学習で感じたデメリット
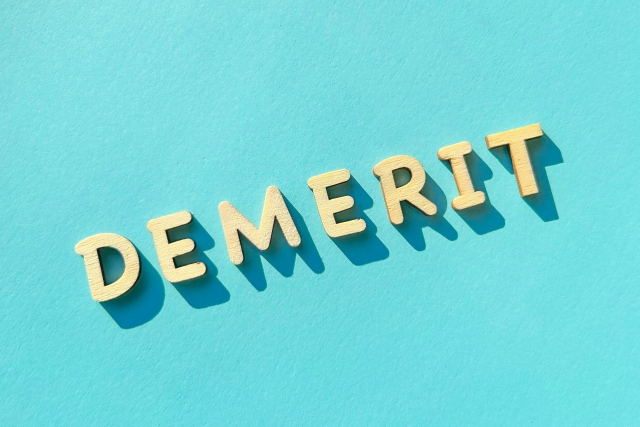
集団で学ぶ良さを得にくい
教室に通っていれば、やる気がない日でも、周りの友達に刺激を受けて頑張れることがありますよね。
誰かと一緒に勉強することで「自分もやらなきゃ」と気持ちが引き締まることも。
また、周囲と自分の学習レベルを比べて、今の立ち位置を客観的に知ることもできます。
お互いに高め合える環境という意味では、集団学習ならではのメリットです。
一方で、タブレット学習は基本的に“ひとり学習”。
強い意志がないと、かえって続けにくい面もあるかもしれません。

ちなみにスマイルゼミにも、
「みんトレ(全国の子どもと対戦できるモード)」があります。
効果はありそうですが、教室でのリアルなやりとりと比べると、
正直、うーん……という感じですね。
目や身体への影響が心配
タブレット学習は画面を見続けるため、以下のような心配も出てきます。
- 目が疲れる
- 視力が低下する
- 姿勢が悪くなる
子どもたちのは、まだまだ発達途中。
身体への影響も考えて、使いすぎないように気をつけてあげたいですよね。
時間を決めて使う、途中で休憩を入れるなど、親のサポートが必要です。
紙の教材に切り替えられるか不安
タブレットは、画面がサクサク進み、効果音やミニゲームも満載。
「子どもが夢中になる」仕組みがたくさん詰まっています。
でも裏を返せば、それは刺激が強いからこそ。
これに慣れてしまうと、紙の教材(=静かで地味)への移行がスムーズにいくか、ちょっと心配です。
わが家ではそれを気にして、以下の工夫をしながら使っています。
- 時間を制限して使うこと(依存防止)
- 読書は紙の本でする(紙媒体への慣れ)
紙の本に触る習慣もつけ、刺激の少ない教材にも慣れておくことが、将来の学習につながると考えています。
スマイルゼミを選んだ理由

数あるタブレット学習サービスの中で、わが家が選んだのは「スマイルゼミ」でした。
その理由は、最初にお話しした「小学校入学前に、学ぶ自信をつけてあげたい」という目的にピッタリだったからです。
無学年学習「コアトレ」で先取り&さかのぼり学習ができる
スマイルゼミの「コアトレ」は、学年にとらわれずに学べる無学年方式の学習モードです。
子どもの理解度にあわせて、どんどん先取り学習をすることができます。
長男は算数好きで、年長時点で割り算(小3)まで進んでいました。
そんな長男も、今や小学生。
幼児コースのときから「コアトレ」で先取り学習をしていたので、学校の勉強で困っている様子は全くありません。
学習習慣をつける工夫がたくさん
スマイルゼミは、毎日の取り組みを続けやすくする工夫も満載。
- 毎日ミッション3講座、15分程度の学習
- 「きょうのできた!」で振りかえり、親との共有
- 「ごほうび」でカードやマイキャラ着せ替えパーツ集め
- スタンプカード
- イベント開催
学習の時間設定15分と短めなのも、「もうちょっとやりたい」という気持ちから「また明日」と、飽きずに続けてもらうための設定だとか。
これらを通して感じたのが、スマイルゼミが「学習習慣を身につけること」を重視して作られているということです。
その考えに共感したのも、スマイルゼミを選んだ理由です。
おわりに
タブレット学習は、子どもの興味を引きやすく、自宅でできるなどのメリットがあります。
一方で、集団ならではの刺激や、目・姿勢への影響など、気をつけたいポイントもあります。
何事も、一長一短。
ご家庭の状況やお子さんの性格にあわせて、うまく取り入れるのが大切だと感じました。
わが家の体験談が、少しでもどなたかの参考になれば幸いです!