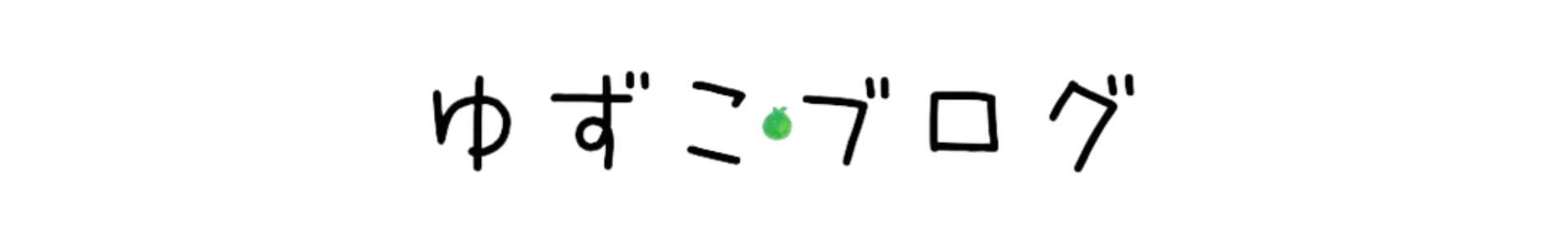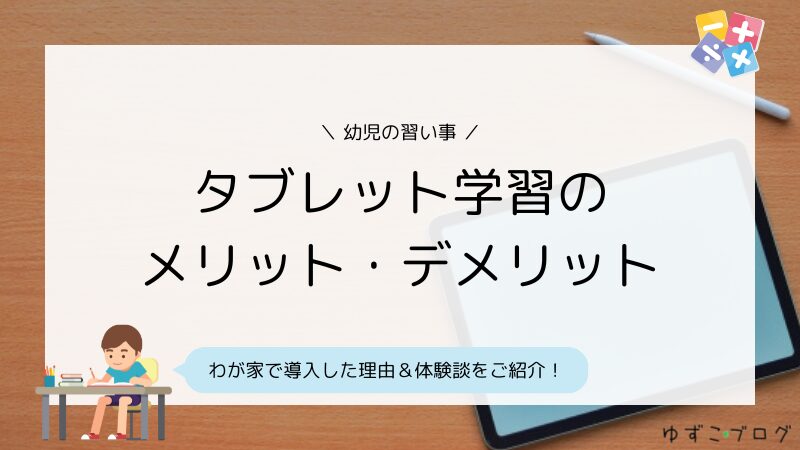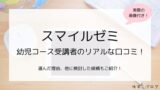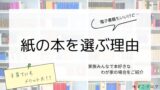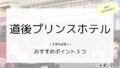わが家は兄弟で、タブレット型学習教材「スマイルゼミ」を受講しています。
親世代が子供のころにはなかった、タブレット学習。
自分に経験がないぶん、導入時にはたくさん悩みました。
- わが家がタブレット学習をはじめた理由
- タブレット学習のメリット・デメリット
わが家の検討した経緯など、体験談も含めてご紹介します。
子どもの習い事選びに迷っている方、よければ参考にしてくださいね。
わが家がタブレット学習をはじめた理由

幼児期から学習系の習い事をしたい
もともと、幼少期から学習系の習い事はさせたいと考えていました。
小学校入学時に、勉強に苦手意識をもたないよう備えたいというのが目的です。
学校で集団学習が始まると、「あーこれ知ってる!自分は勉強が得意かも!」と思うのか、「自分は人よりできないかも……」と感じるのか。
そのセルフイメージは、後の人生にも長く影響を与え続けると思います。

勉強の好き嫌いって、案外ここで大きな分岐点がある気がしています。
大人になっても、勉強は続きます。
どうせするなら、得意で楽しめるほうが人生おトクですよね。
できればわが子には、良いセルフイメージを持って、学習のスタートをきってほしいです。
そのために備えたくて、幼児期から学習系の習い事をはじめることにしました。
教室への送り迎えが不要
長男の習い事を検討していたときの状況です。
- 長男4歳年少、年中から学習スタートしたい
- すでにスイミングは習っていた
- 次男1歳、赤ちゃん連れの送迎が大変
- 学習ドリルをやってみるも、うまくいかず
親が子どものころ「KUMON(公文式教室)」に通っていた経験もあり、まずは公文を最初に検討しました。
ちょうどまわりの子も通い始めたところで、「お友達と一緒ならやる気も出るかも!」と思い、より惹かれていました。
しかし公文は、週2回教室に通う必要があります。
家からの距離が、微妙だったんですよね……
それと、長男は当時すでにスイミングに通っていたのですが、週1回でも子どもたちを連れていくのが想像以上に大変で……
これ以上、習い事の送迎が増えるのは正直しんどい、と当時感じていました。
そこでためしに、書店で買ってきたドリルを自宅でやってみたのですが、長男まったく気乗りせず。
やる気のない子どもに、一生懸命ドリルをさせようとする私。

親子ともに、どんどん疲れていきました……
これで勉強が嫌いになったら本末転倒!
このような経験から、タブレット学習という新しい選択肢を考えてみたのです。
「これからの時代を生きる息子たち、デジタル機器に親しんでおくのもまぁ悪くないか!」と思い、未知の領域でしたが思いきって採用しました。
タブレット学習のメリット・デメリット

タブレット学習のメリット
子どもが楽しんで勉強してくれる
タブレットでは、動画や音声をつかった学習ができます。
子どもの興味を引きやすいだけでなく、英語のリスニングなどもできるのは大きなメリットですよね。
学習後のミニゲームなど、ちょっとしたごほうび要素もあるので、子どもが楽しんで自発的にやってくれます。
学習ドリルでイヤイヤ勉強させられるよりは、よほど効果的だと感じます。

まずはタブレット学習を入口に、勉強を楽しいものだと思ってもらおう!
そして学習習慣を身につけてもらおう!
こんな風に考えています。
「ごほうび要素がないと勉強しない!」となっては困りますが、そこは成長とともになんとかなるかな、と。
そもそもの勉強へのとっかかり、はじめの第一歩としてタブレットを利用するのは、十分アリだと感じています。
それぞれに合わせた学習内容
タブレットが子どもの学習内容を記憶・整理してくれるので、個別のペースに合わせて学習が進められます。
理解度にあわせて、学習内容をおすすめしてくれたりするので、とても心強いです。
苦手な部分を重点的に復習したり、得意な部分をさらに深めたり。
一人ひとりに最適な学習が提供されるのは、とっても便利だと思います!
自宅で完結できる
先の「教室への送り迎えが不要」の項でも触れましたが、習い事の送迎って大変なんですよね……!
子どもが複数人いたり、赤ちゃんだったり、イヤイヤ期の子だったりするとなおさらです。

思い通りには動いてくれないですよね、子どもって。
習い事の時間にまにあうか、毎回ヒヤヒヤしています……
しかしタブレット学習なら、そのストレスもありません。
わが家では毎日、登園前に15~20分、スマイルゼミに取り組んでいます。
自宅で完結してくれるのって、想像以上にありがたいです。
教室の行き帰りの移動もないので、あいた時間を他のことに使えるのも良いですよね。
費用がお手頃
教室での習い事に比べて、タブレット学習は安価で受講できます。
学習教室いくつかと、料金をざっと比較してみました(年中を想定)。
| 学習教室 | 月額の目安 |
|---|---|
| KUMON | 7,150円~ (1科目) |
| 学研教室 | 6,930円~ |
| 七田式教室 | 15,400円~ |
| ドラキッズ | 11,000円~ |
| タブレット学習 | 月額の目安 |
|---|---|
| スマイルゼミ | 3,630円~ |
| こどもちゃれんじ | 1,980円~ |
| RISUきっず | 2,948円~ |
それぞれの最低価格、月謝のみを単純比較しました。
- それぞれに特徴があり、学習内容も異なる
- コースによって料金が異なる場合あり
- 入会金、教材費などが追加でかかることも
そのため一概に比較はできませんが、明らかに価格帯が違うのはわかります。
毎月のことなので、家計への影響も大きいですよね。
ここで浮いた分で、また別の習い事をさせてあげられるかもしれません!
ちなみに、タブレット学習のなかでもスマイルゼミを選んだ理由は別記事にまとめています↓
タブレット学習のデメリット
集団のメリットが享受できない
やる気が出ないときでも、教室に行けば友達がいます。
みんなが勉強している姿を見て、自分もやる気になることってありますよね。
それに勉強のレベルも、周囲と比較するからこそ自分の立ち位置がわかります。
お互いに刺激しあって、切磋琢磨できるのが集団のメリットです。
完全に一人で、強い意志を持って勉強を続けるほうが難しくありませんか?
とても孤独な戦いです。
集団の効果というのは、タブレット学習では得られないものだと思います。

ちなみにスマイルゼミでも、「みんトレ」という対戦形式の学習があります。
個人学習の弱点を補おうとする試みかな?と思います。
効果はなくはないですが、教室と比べると、うーん……という感じですね。
視力への影響が心配
長時間タブレットを使うことで、
- 目の疲れ
- 視力の低下
などを引き起こす可能性があります。
子どもたちは、まだまだ発達途中。
身体への影響も考えて、使いすぎないように気をつけてあげたいですよね。
紙ベースでの勉強に移行できるか
タブレット学習は、画面が次々と変わり、いろんな音がなり、ミニゲームもある……
子どもの興味を引きやすいのですが、それは刺激が強いからなんですよね。
そのメリットを活かそうと利用していますが、これから紙の教材(超・低刺激)にちゃんと移れるかは少し心配です。
わが家ではそれを気にして、以下の工夫をしながら使っています。
- 時間を制限して使うこと(依存防止)
- 読書は紙の本でする(紙媒体への慣れ)
おわりに
わが家でタブレット学習を導入した経緯と、そのメリットデメリットをご紹介してきました。
何事も、一長一短。
長所と短所は表裏一体ですよね。
タブレット学習の特徴をきちんと把握して、子どもの様子も確認しながら、今後も取り組んでいきたいと思います。
わが家の体験談が、少しでもどなたかの参考になれば幸いです!